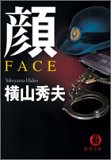そうです。タイムトラベルもの大好きです(笑)
四六版ハードカバーの(上)(下)ということで、すっごい長い恋愛小説?SF小説?です。主人公はクレアというタイムトラベラーの奥さんになる女性。夫の名はヘンリー。彼は、時間同一性障害とも言うべき、自分ではどうにも制御できず、突然いろんな場所にタイムトラベルしてしまうという病気(?)です。彼は、将来自分の奥さんになる予定の6歳のクレアの前に現れるのですが、ヘンリーが「タイムトラベルしてきた」というのをきちんと信じるのです。タイムトラベルという歪んだ時間軸でも、真実は1つで変えられない、そんなことを考えさせられます。
小説の中では、クレアが6歳から82歳まで描かれます。クレアはいつもいつも突然いなくなってしまうヘンリーを待っています。最後の47年間は、クレアはヘンリーが現れるのを待つのですが、彼女は6歳から82歳まで一貫してヘンリーのことが大好きで愛しているのです。そこには時間という本来は絶対にゆがまないものがゆがんでも、変わらない愛がある。そんなふうに思わずにはいられません。
「愛する人は未来からやってきた。やがてくる別れの日を知っていた。」っていうのがキャッチコピーですが、ヘンリーは過去も未来も自分の意思と関係なくタイムトラベルしてしまうのでいろんなことを知ってしまいます。中にはうれしいものもあるけど、悲しいものもあります。でも、ヘンリーはそれを受け止めて生きて行くんですね。それは、ある意味あるがままを受け入れるという、究極の心理状態がそこにあって、「果たして自分だったらどうだろうか?」と考えずにはいられません。
アルバという二人の娘が生まれるエピソードは、ちょっとどきっとさせられます。これは詳しく触れすぎると読む楽しみがなくなるので書くのはやめておきましょう(笑)
僕がこの小説が他の小説と違うと思うのは、たいていのタイムトラベラー小説は、タイムトラベラーという人は未来をしっているスーパーマンでヒーローなのです。ところが、この小説のタイムトラベラーは、自分が望んでもいないのにタイムトラベラーであることに苦悩し耐える、いわば普通の人なのです。普通であろうとしても普通でいられない、そのヘンリーの苦悩が痛いほど伝わってきます。
もし、本当にこんな病気が存在したら、すごい不便かもしれないという、正気でいられるんでしょうか???
オードリー・ニッフェガーさんは、この作品が処女作だそうです。願わくば、タイムトラベラーであるヘンリーの娘アルバ、彼女もタイムトラベラーなのですが、彼女の視点で描かれた作品を読んでみたいです。彼女が大人になって、「ヘンリーが現れるのを待つ母」を見ながら、どのようにすごしているのか、そんな次回の作品に期待を持ってしまった作品でした。
ちょっと長いですが、下巻の後半は悲しく悲しくて大変です。ハンカチじゃなくタオルのご用意を。
 特に仕事の予定のない久々の日曜日だったのですが、「八重洲ブックセンターおもしろいよ!」とのことだったので行ってきました。ところで、どうして入口に二宮金次郎の金の人物像(金の銅像って書きそうになりました)があるんでしょうね?なぜか、近隣のそば屋の前にも二宮金次郎像があったりして、東京駅界隈の人は二宮金次郎とゆかりがあるんでしょうか?でも、二宮金次郎って小田原の人だよねぇ?
特に仕事の予定のない久々の日曜日だったのですが、「八重洲ブックセンターおもしろいよ!」とのことだったので行ってきました。ところで、どうして入口に二宮金次郎の金の人物像(金の銅像って書きそうになりました)があるんでしょうね?なぜか、近隣のそば屋の前にも二宮金次郎像があったりして、東京駅界隈の人は二宮金次郎とゆかりがあるんでしょうか?でも、二宮金次郎って小田原の人だよねぇ? お昼は近所の北海道物産センターみたいなところで、スープカレーを食べました。結構いけます。っていうか、おいしかった、普通に。
お昼は近所の北海道物産センターみたいなところで、スープカレーを食べました。結構いけます。っていうか、おいしかった、普通に。
 最後は、北海道物産館に戻って、チーズケーキを買って帰って家で食べました。このチーズケーキ、すげーうまかったっすよ。
最後は、北海道物産館に戻って、チーズケーキを買って帰って家で食べました。このチーズケーキ、すげーうまかったっすよ。